セミナー報告:災害×ダイバーシティセミナー『原発事故、ひとりひとりの記憶 3.11から今に続くこと』をもとに
開催日時:2025年1月23日(木)16:20~17:50
開催方法:ハイブリッド アーカイブ配信はこちらから
開催場所:埼玉大学 総合研究棟1号館 シアター教室
参加者:50名(オンライン参加25名)
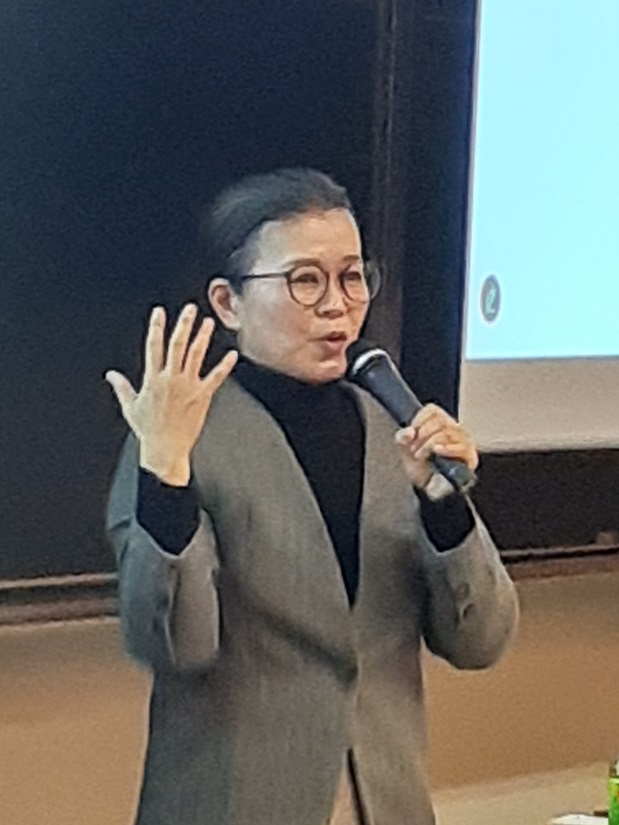
講師:吉田千亜さん(フリーライター)
プロフィール:福島第一原発事故後、被害者・避難者の取材、サポートを続ける。著書に『原発事故、ひとりひとりの記憶 3.11から今に続くこと』(岩波ジュニア新書)、『孤塁 双葉郡消防士たちの3・11』(岩波書店)、『ルポ 母子避難』(岩波新書)、『その後の福島-原発事故後を生きる人々』(人文書院)。共著『原発避難白書』(人文書院)など。『孤塁』で、講談社 本田靖春ノンフィクション賞(第42回)、日隅一雄・情報流通促進賞2020大賞、日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞(第63回)受賞。
2025年1月23日に、埼玉大学社会変革研究センターレジリエント社会研究部門・埼玉大学ダイバーシティ推進センター主催、協賛・自然災害研究協議会関東地区部会で、災害×ダイバーシティセミナーとして<『原発事故、ひとりひとりの記憶 3.11から今に続くこと』をもとに>を開催しました。
セミナーでは、2011年の福島原発事故後、被害者・避難者のサポートを行いながら、ライターとして、多くの被災当事者の話を聞き、著書にまとめ、発信してきた講師の立場から、福島原発事故がもたらした課題や、現在に続く困難についてのお話がありました。また、途中、原発事故がもたらした被害とはどのようなものか、という問いかけがなされ、直接的な事故後の放射能汚染や、それにともなう健康への影響のほか、住み慣れた土地を追われること、避難を余儀なくされることによるコミュニティや文化の喪失、はく奪も、被害と捉える必要があると話されました。同時に、事故の加害とはどのようなものか、という問いもあり、原発事故を起こしたことのほかに、事故の反省がなされていないこと、また、情報が明らかにされないことや、被害者の声がなかったことにされること、さらには、「知らない」という立場でいることも広い意味での加害に含まれるのではないか、という問題提起がありました。
吉田さんは、セミナーの終わりに、原発事故をきっかけに避難した女の子の声として次の声を紹介されました。「どんどんなかったことにされていて、それだけは本当になかったことにしてほしくないですね。だから自分にできることもしているし、支援に関わることもやっていますし、語り部のようなこともやっています。すごい勢いで風化していることを感じています」。
そして、最後に、福島原発事故の問題について、是非、関心を持ち、引き続き、考えていってほしいと話されました。
本セミナーは、授業(ダイバーシティ福祉論)の一環でもあり、学生と一般市民の方とが同時に受講しました。
◆アンケートから参加者の声の一部を抜粋して紹介します。
・福島原発の被害を受けた方々の生の声を紹介いただけたこと、構造的な加害の問題について学ぶことができたことがよかった。(一般)
・3.11被災者の各自の固有の悩みやつらさ、課題などを提示した充実した講演会でした。吉田さんの被災地・被災者をおもう気持ちの熱さを感じると同時に、豊富なデータをみることで課題もみえ、まだまだ問題は終わっていないと感じることができた。(一般)
・お話を聞いて、原発事故について新たな知識が増え、「当事者意識」が高まりました。原発事故を構造的に理解するということで加害者、被害者、傍観者の立場を考えることができました。これにははっきりとした正解がなくて、いろいろなとらえ方、分け方があることを知りました。その一つに本当の被害者は次世代の子どもたちだというのがありました。たしかにその通りだなと感じたのと同時に今成人として生きている自分には次世代の子どもたちの権利を守る責任があり、自分はそのようなことができているだろうかと見つめなおす機会となりました。(学生)
・原発事故が人々に及ぼす影響がいかに多岐に渡るかということは知っていたが、今回のお話で、現在でも避難を続けざるを得なかったり、自分の生まれ育った場所に帰ることができなかったりする状態が続いていることを知った。もしも自分の地元が100年帰れませんと言われたらどういう気持ちになるだろうと考えたときに、今まであった人の暮らしとか、自分が生まれるずっと前のことも失われるような気がした。(学生)
