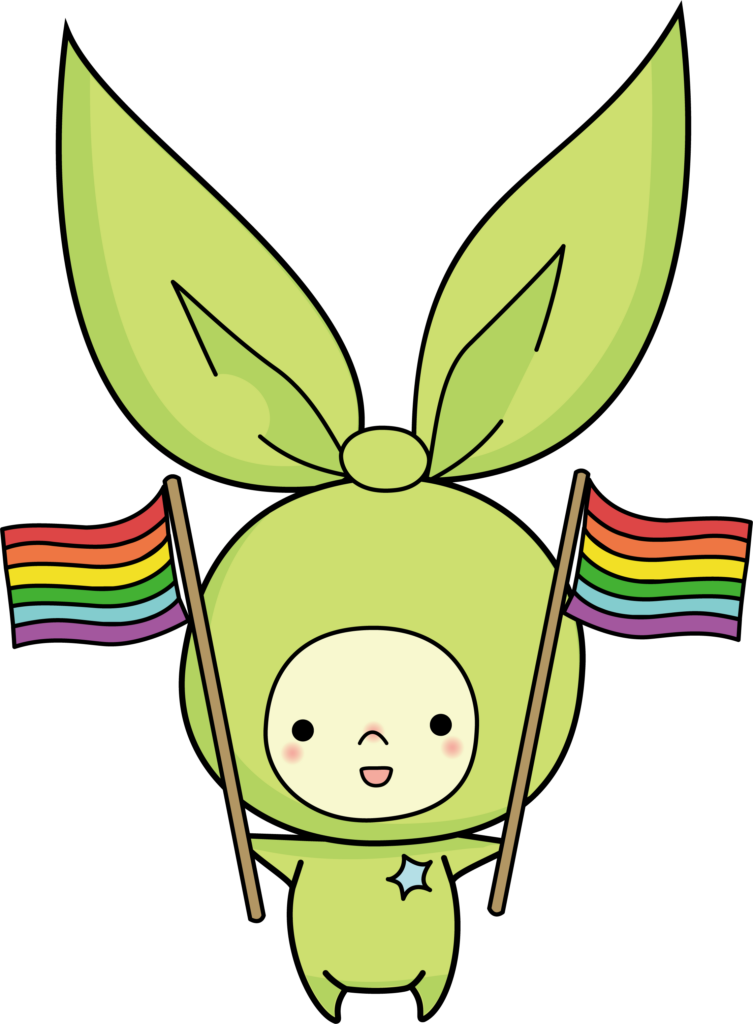ダイバーシティ推進センターとは
ダイバーシティ推進センターの歩み

副学長(ダイバーシティ推進担当) 田代 美江子
埼玉大学では2009年に、第2次男女共同参画基本計画に基づき、埼玉大学男女共同参画室を設置し、翌年12月に「埼玉大学男女共同参画宣言」を表明しました。この男女共同参画室の取り組みは、2017年、文部科学省科学人材育成事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」に、埼玉大学が選定されたことによって大きく前進します。これにより、ダイバーシティ推進オフィスを設置し、女性教員採用・登用促進や次世代育成に関する具体的目標に向かって努力してきました。また、この事業の中で、埼玉県地域の女性研究者・技術者の活躍推進を進めるため、埼玉県との協働による「彩の国女性研究者ネットワーク」を組織したことは、埼玉大学のダイバーシティ推進の基盤となっています。
2020年度には、男女共同参画室はダイバーシティ推進室となり、「埼玉大学ダイバーシティ宣言」を出しました。これは、単なる名称の変更ではなく、これまでの「女性研究者支援」に加え、本学全体でダイバーシティ推進へ取り組んでいくのだという決意表明でもあります。
実際、学長のリーダーシップ、そして大学執行部のサポートの中、ダイバーシティ推進室の体制は、本学の中でもいち早く教職協働体制を実現しました。それだけでなく、2021年に策定した、2022年度からの第4期の目標と計画において、埼玉大学におけるダイバーシティ推進とそのための体制の充実は、以下のように明確に位置づけられたのです。
「多様性と包摂を尊重するダイバーシティ環境を地域に根付かせるため、ダイバーシティ推進室の体制を強化し、埼玉県内のダイバーシティ推進のハブとなる組織を構築するとともに、彩の国女性研究者ネットワークを基盤とした埼玉県内の大学・企業・行政と協働し、多様性や包摂に対する地域市民の意識向上のための中心的役割を果たす。」
この計画に基づき、2022年度から、ダイバーシティ推進室はダイバーシティ推進センターとして再編され、専任教員が1名から3名へ、さらにその業務を支えるための産学官連携・ダイバーシティ推進課が設置され、その体制は大きく飛躍しました。新たな体制のもと、これまでの取り組みをさらに充実させると共に、①ダイバーシティ課題解決教育プログラムの企画・開発と提供、②ダイバーシティの観点からの文理融合・共同研究企画支援にも精力的に取り組んでいきます。学生を含む全ての大学構成員と共に、また、地域との連携と協働体制を確立しながら、世界的に大幅な遅れをとっている日本のジェンダー平等、ダイバーシティ環境の進展のために、さらなる努力を積み重ねていきます。
「埼玉大学ダイバーシティ宣言」の実現を目指して

ダイバーシティ推進センター長 北田佳子
「埼玉大学ダイバーシティ宣言」には、「多様な人々の人権が尊重されるという『多様性』(ダイバーシティ)の理念と、その多様な誰もが安心して学び、働き、活躍できる機会を保障するという『包摂』(インクルージョン)の理念を、大学のすべての取組の礎」とすることを明言しています。
近年、日本でもこの「多様性(ダイバーシティ)」という言葉をよく目にするようになりました。政治、経済、医療、福祉、教育等、さまざまな分野において、多様な人々が集まることで組織が活性化したり、新しい製品や制度が産み出されたりすることが期待されています。しかし、組織の活性化や新製品・新制度の創出という目的のために「多様性」(ダイバーシティ)を重視するのではない、ということに留意する必要があります。「多様性」(ダイバーシティ)を重視する理由は、あくまでも「多様な人々の人権が尊重される」ためであり、組織のメンバー一人ひとりの人権が尊重された結果として、活性化や創出が実現するのだと考えられます。
また当然ながら、多様な人々が集まれば対立や軋轢も生じやすくなります。そのため、組織を安定させようとして、「包摂」(インクルージョン)と称しながら、組織のなかの多数派に少数派を取り込んでいく「同化」(アシミレーション)が起きているケースも少なくありません。誰しも不安定な組織より安定した組織に身を置きたいと思うのは当然のことです。しかし、一度立ち止まって、その「安定」は誰の立場からみたものなのかを問い直してみることが大切でしょう。自身が「安定」と思っている状態が、本当に「誰もが安心して学び、働き、活躍できる機会を保障する」状況となっているのかを常に問うことが、「同化」ではない「包摂」を実現する歩みとなります。